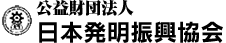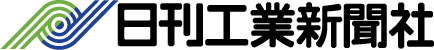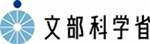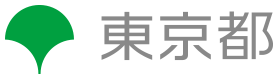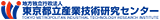2025年は「昭和100年」にあたります。“激動の時代”と言われた昭和ですが、一方で日本では電気炊飯器や新幹線、カーナビゲーションシステムなど多くのものが発明され、人々の生活を豊かなものにしてくれました。
平成を経て令和の時代の足元では、生成AI(人工知能)が話題となっています。精度が向上し、使いやすさや手軽さもあり、一気に普及が進みましたが、AIの発明に特許を認めるかどうかといった新たな議論も生まれました。ただいずれにしろ、AI技術の進化は目覚ましく、例えばスマートフォンが普及し、私たちの行動を変えていったように、人々の生活にとって不可欠なものになっていくと考えられます。
また、今年は大阪市の人工島・夢洲(ゆめしま)で大阪・関西万博が開幕しました。資材や人手不足・準備期間の短さによりパビリオンの建設が遅れる、前売りチケットの販売不振など紆余曲折ありましたが、無事に開幕することができたのは喜ばしいことです。
世界初の万国博覧会は1851年にイギリスのロンドンで開催され、目覚まし時計や印刷機、蒸気機関車などが展示されました。今では当たり前のものでも、当時は珍しく、来場者の興味をかき立てたと思われます。
2025年の今回は「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマとし、158の国・地域が参加しました。空飛ぶクルマや次世代エネルギーによる発電、人工多能性幹細胞(iPS細胞)から作製された実際に拍動する「iPS心臓」など数々の新技術がお披露目され、多くの人にワクワクやドキドキを与えてくれました。実用化され、私たちの生活にとって当たり前になるにはまだ課題がありますが、やがて自分の身近に訪れるだろう未来を感じた人は少なくないでしょう。
時代によって求められる技術や製品は異なりますが、共通するのは少しでも我々の生活を良くしたい・便利にしたい、社会に貢献したいといった人々の熱い思いです。もちろん、最終製品だけではなく、外部から人の目に触れることがないモノ、部品一つでも、そこには多くの英知と努力が結集しています。
私たちの暮らしには、常に困難や予測不能な事態がつきものです。2024年1月に起きた能登半島地震はあらためて地震の怖さを私たちに見せつけました。この爪痕は、まだ完全には癒えていません。地震や台風、豪雨、山火事など自然災害が起こるリスクは常にあり、新型コロナウイルス感染症も喫緊の脅威は薄れたとはいえ、いつ、どこで新たな感染症がはやるか分からない恐怖があります。
さらには、国際情勢の不安定化もあり、先が見通しづらく、不確実性が増している今の世の中ですが、高い志と、たゆまぬ探究心を持って挑んだ発明が私たちの明るい未来を切り開いていくことはこれからも変わりありません。
2024年7月にお札のデザインが一新され、新1万円札の肖像に選ばれた渋沢栄一の言葉に「もうこれで満足だという時は、すなわち衰える時である」というものがあります。「発明大賞」の受賞企業においても、どのような環境下でも、決して現状に満足することのない姿勢が新たな発明につながっていきました。
「発明大賞」は創設から51回を迎えます。中堅・中小企業、研究者や個人の発明家を対象に、優秀な発明考案を生み出し、成果をあげた企業や個人をこれまで表彰してきました。
特色としては、発明大賞の歴代受賞者をはじめとする幅広い企業や個人のネットワークが、発明を生み出す環境を育んできたことです。一つの発明が、世の中を変え、我々は、発明により実現したことによって便利さを享受し、日々暮らしています。先人が築いた業績、数多くの発明がつながることにより生まれる製品やサービスにより、我々がその恩恵を受けていることは間違いありません。発明が新たな可能性を広げていきます。
ぜひ、発明を通じて、その未来を切り開く人々の輪に加わっていただければと願っています。
皆様の応募を心よりお待ちしております。